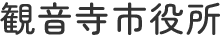本文
障がい福祉サービスの利用者負担
障がい福祉サービスの利用者負担
利用者負担
原則1割の自己負担が必要となりますが、世帯の所得に応じて自己負担の上限が設定されます。
| 区分 | 世帯状況 | 負担上限額 | |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 | |
| 一般1 | 市民税課税世帯 | 障がい児の場合 市民税所得割が28万円未満 |
4,600円 |
| 障がい者(施設に入所する方を除く)の場合 市民税所得割が16万円未満 |
9,300円 | ||
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 | |
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
| 種別 | 世帯の範囲 |
|---|---|
| 18歳以上の障がい者 | 障がいのある方とその配偶者 |
| 18歳未満の障がい児(施設に入所する18.19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
その他、サービスにより、医療型個別減免や補足給付、多子軽減措置等があります。
高額障害福祉サービス等給付費
同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる等、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請により「高額障害福祉サービス費」「高額障害児入所給付費」または「高額障害児通所給付費」として支給されます。
合算の対象となるサービス
以下のサービスの利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
・障害者総合支援法に基づくサービス
・介護保険法に基づくサービス
※ただし、一人の方が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除きます。
・補装具費
・児童福祉法に基づくサービス
支給額
基準額(37,200円※)を超えた分(世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額の差額)が支給されます。
※利用したそれぞれのサービスの受給者証および支給決定通知書に記載された上限額のうち、一番高い額が当該月の基準額となります。