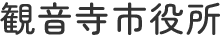本文
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
※令和6年11月から児童扶養手当法等の一部が改正されます。
・第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
・全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ等
支給要件
■母子家庭
次のいずれかに当てはまる児童を監護している母または母に代わって養育している方(養育者)
1 父母が離婚した後、父と生計を別にしている児童
2 父が死亡した児童
3 父が重度の障害の状態にある児童
4 父の生死が明らかでない児童
5 父に1年以上遺棄されている児童
6 父が母の申立てにより保護命令を受けた児童
7 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
8 母が婚姻によらないで懐胎した児童
■父子家庭
次のいずれかに当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父または父に代わって養育している方(養育者)
1 父母が離婚した後、母と生計を別にしている児童
2 母が死亡した児童
3 母が重度の障害の状態にある児童
4 母の生死が明らかでない児童
5 母に1年以上遺棄されている児童
6 母が父の申立てにより保護命令を受けた児童
7 母が引き続き1年以上拘禁されている児童
注)ただし、次の場合、手当は支給されません。
●児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
●児童や手当を受けようとする父若しくは母または養育者が日本国内に住んでいないとき
●父または母が婚姻しているとき(婚姻の届け出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
手当月額(令和7年4月分の支給から)
| 対象児童 | 全部支給のとき | 一部支給のとき |
|---|---|---|
| 1人目 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
| 2人目以降加算 | 11,030円 | 11,020円~5,520円 |
注1)一部支給額は対象児童の数や受給資格者(父・母・養育者)の所得等により10円単位で決定されます。
注2)受給資格者の所得等により手当の全部が支給停止される場合があります。
注3)2人目以降加算は、1人あたりの加算額です。
所得制限限度額
前年の所得が、下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。
扶養義務者の所得が所得制限限度額以上になると、その年度の手当の全部が支給停止になります。扶養義務者とは、同居している受給者の父母・兄弟・姉妹・祖父母・子等のうち、最も所得の高い人をいいます。
| 扶養親族の数 | 令和6年分所得の所得制限限度額 ( )書きは給与所得者の場合、所得に対応する収入額です | ||
|---|---|---|---|
| 請求者本人 |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 |
||
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 690,000円(1,420,000円) | 2,080,000円(3,343,000円) | 2,360,000円(3,725,000円) |
| 1人 | 1070,000円(1,900,000円) | 2,460,000円(3,850,000円) | 2,740,000円(4,200,000円) |
| 2人 | 1,450,000円(2,443,000円) | 2,840,000円(4,325,000円) | 3,120,000円(4,675,000円) |
| 3人 | 1,830,000円(2,986,000円) | 3,220,000円(4,800,000円) | 3,500,000円(5,150,000円) |
| 4人以上 | 以下所得については380,000円ずつ加算 | ||
限度額に加算されるもの
(1)請求者本人の場合(控除額)
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る)1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養親族の場合
・老人扶養親族1人につき6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-下記の諸控除-80,000円(社会保険料相当額)+養育費の80%
| 障害者控除 | 27万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 |
| 勤労学生控除 | 27万円 |
| 寡婦控除 | 27万円 |
| ひとり親控除 | 35万円 |
| 医療費控除 | 住民税で控除された額 |
| 配偶者特別控除 | |
| 小規模企業共済等掛金控除 | |
| 雑損控除 | |
| 公共用地取得による土地代金の特別控除 |
長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る以下の特別控除額 (1) 公共事業などのために土地建物を売った場合 5,000万円 (2) 居住用財産を売った場合 3,000万円 (3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合 2,000万円 (4) 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合 1,500万円 (5) 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合 1,000万円 (6) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合 800万円 (7) 上記の(1)~(6)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額 5,000万円 |
注)令和3年度以降の母による受給の場合は、寡婦控除・ひとり親控除は、適用されません。または父による受給の場合は、ひとり親控除は適用されません。
手当額の計算方法
第1子手当額=46,690円-((受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0256619+10円)
第2子以降加算額=11,030円-((受給者の所得額-所得制限限度額)×0.0039568+10円)
※受給者の所得額…収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※所得制限限度額…所得制限限度額表の本人(母、父または養育者)欄の「全部支給の所得制限限度額」に金額であり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
※計算の基礎となる46,690円、11,030円の金額、0.0256619、0.0039568の係数は固定された数値ではありません。物価変動等の原因により改定される場合があります。
申請手続きについて
申請者本人が、認定請求書に必要書類を添えて子育て支援課及び各支所の窓口で申請してください。
ご自身が対象かどうかや必要書類は、個々のご家庭の状況により異なりますので、詳しくは子育て支援課にご相談ください。
申請は毎月月末締切で、手当は申請月の翌月から計算されます。なお、審査には通常2,3か月程度かかります。
手当の受給開始から5年等を経過した場合の一部支給停止について
母または父に対する手当は、手当の受給開始から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときのいずれか早い月から、手当額の一部が支給停止されることとなっています(認定請求をした日に、満3歳未満の児童を監護している受給資格者については、児童が満8歳に達した月の翌月から手当額の一部が支給停止されることとなっています)。
ただし、就労している方、求職活動中の方、自立に向けた職業訓練中の方、あるいは障害や疾病などにより就労できない正当な理由がある方などは、そのことを証明する書類を添えて「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出することにより、次の現況届の時まで、従来どおりの支給を受けることができます。
手当を受けている方の届出
受給中は次の届出が必要です。
届出が遅れたり、提出しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、支給済みの手当を返還していただくことになりますので、必ず本人が、提出してください。
| 現況届 |
受給資格者全員が、毎年8月1日から8月31日までの間に必要な書類とともに提出します。 この届を提出しないと、その年の11月分以降の手当の支給を受けることができなくなります。 また、2年間現況届を提出しないでいると、時効により受給資格がなくなります。 |
|
額改定届・請求書 |
対象児童に増減があったとき |
|
資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき |
|
一部支給停止適用 除外事由届出書 |
受給開始から5年または支給要件に該当した月から7年を経過するとき以降の毎現況届時に関係書類とともに提出します。 |
| その他の届出 |
住所・氏名・銀行口座を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得制限限度額以上の扶養義務者と生計同一となったとき、または別居したとき、公的年金を受給するようになったときなど |
次のような場合は受給資格がなくなります
〇手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居等を含みます)
〇母子家庭…児童を監護・養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます)
〇父子家庭…児童と生計が別になったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます)
〇受給資格者または児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき
〇児童が、死亡したり行方不明になったとき
〇遺棄などの理由で、家庭を離れていた父または母が、電話や手紙で連絡してきた、仕送りがあったまたは帰宅したとき
〇刑務所に拘禁されていた父または母が、出所したとき(仮出所を含む)
※事実婚が疑われる場合は、児童扶養手当支給要件該当の有無を調査することがあります。ご理解ください。
※児童扶養手当法第35条により、偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
支払いスケジュール
手当は請求日の属する月の翌月分から支給され、年6回奇数月に支払月の前月分までの2ヶ月分が支払われます。
支払日は各支払月の11日(土・日曜、祝日の場合は、その前営業日)です。
公的年金との併給について
児童扶養手当は、公的年金等(※1)を受けることができるときは手当額の全部または一部を受給できません。
障害基礎年金等(※2)を受給されている方については、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。 障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(※3)は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
障害基礎年金等を受給している受給資格者は、支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※4)が含まれます。非課税所得である公的年金給付等を課税所得の公的年金等とみなし、公的年金等控除等を適用して算定した額を「所得」に加算します。
※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
※3)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
※4)非課税公的年金給付等とは、障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償などです。
公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し、子育て支援課への手続きが遅れた場合、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。手続きは早めに行うようにご注意ください。
【お問い合わせ】
本庁 子育て支援課児童福祉係 Tel 0875-23-3962
大野原支所 市民係 Tel 0875-54-5700
豊浜支所 市民係 Tel 0875-52-1200
伊吹支所 市民係 Tel 0875-29-2111