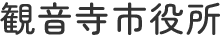本文
後期高齢者医療制度とは
制度の概要
高齢化に伴う医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするため、75歳以上の高齢者を対象にその心身の特性や生活実態などを踏まえて、今まで加入していた医療保険から独立した制度として、平成20年4月に創設されました。
制度の運営
香川県内すべての市町が加入する「香川県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>」が保険者となり、市町と連携しながら運営しています。各種申請や届出の受付、保険料の徴収などの窓口業務は市が行います。
対象となる方
次の方が香川県高齢者医療保険の被保険者となります。
75歳以上の方
75歳の誕生日から国民健康保険や被用者保険の資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度に加入することになります。加入の手続きは不要です。マイナ保険証(※)も自動的に保険情報が切り替えられますので、継続してご利用いただけます。
75歳の誕生日の前月中旬に、香川県後期高齢者医療広域連合より「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が送られます。資格確認書をご利用の方は誕生日からお使いください。
注意:資格情報のお知らせだけでは医療機関等で保険診療を受けることができません。マイナ保険証の読取りができない医療機関等においては、マイナ保険証とともに資格情報のお知らせを提示することで保険診療を受けることができるようになりますので、大切に保管してください。
※マイナ保険証:保険証として利用できるように登録したマイナンバーカードです。利用登録は、マイナポータルや医療機関に設置されているカードリーダー、市役所市民課またはセブン銀行ATMなどで行えます。
65歳から74歳の方で、香川県後期高齢者医療広域連合が一定の障がいがあると認めた方
一定の障がいのある方は、本人の申請に基づき、香川県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合、65歳より後期高齢者医療制度に加入することができます。
なお、認定を受けていても、75歳になるまでの間は将来に向かって申請を取り下げることができます。
認定を受けられる障がいの程度
- 国民年金法等障害年金証書:1、2級
- 身体障害者手帳:1、2、3級および4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳:1、2級
- 療育手帳:(A)、A
後期高齢者医療制度に加入したい場合は、上記の障がいの程度がわかるもの(障害者手帳など)と、現在加入している健康保険の情報がわかるものを持参し、申請してください。
住所地特例
住所地の特例として、香川県内に住所を有していた方が県外の特別養護老人ホームや介護療養型医療施設等の住所地特例対象施設へ入所した場合には、転出後も引き続き香川県後期高齢者医療保険の被保険者となります。
適用除外となる方
生活保護を受給している方は被保険者となりません。
自己負担割合
医療機関の窓口では、かかった医療費の一部を自己負担します。 自己負担割合は世帯における加入者の住民税課税所得や収入額に応じて、1割、2割(令和4年10月施行)、3割に分かれています。
|
割合 |
所得区分 | ||
|---|---|---|---|
|
3割 (※) |
現役並み所得者 | 現役3 | 課税所得が690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者 |
| 現役2 | 課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | ||
| 現役1 | 課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者 | ||
| 2割 | 一般2 | 課税所得28万円以上145万円未満、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯は200万円以上、 被保険者が2人以上の世帯はその合計が320万円以上の被保険者 | |
| 1割 | 一般1 | 住民税課税世帯で、現役1・2・3(3割)、一般2(2割)に該当しない被保険者 | |
| 区分2 | 世帯全員が住民税非課税で、区分1に該当しない被保険者 | ||
| 区分1 | 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員が所得0円、または老齢福祉年金受給者(年金の所得は、控除額を80万円として計算) | ||
※ 住民税課税所得が145万円以上であっても、下記のいずれかの条件に該当する方のうち、本市において収入情報が確認できる場合は、1割負担または2割負担となります。ただし、収入情報が確認できない場合は、申請書の提出をお願いしております。
- 世帯に被保険者が1人で、被保険者の収入額が383万円未満
- 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の収入合計額が520万円未満
- 世帯に被保険者が1人で、収入が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳~74歳の方がいる場合、その方を含めた収入合計額が520万円未満
注) 住民税課税所得が145万円以上であっても、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者で、世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、1割負担または2割負担となります。
香川県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
お問い合わせ先
・医療給付に関する届出
健康福祉部健康増進課国保医療係
Tel:0875-23-3927
・保険料の内容について
(簡易申告書の受付、保険料など)
総務部税務課市民税係
Tel:0875-23-3922
・保険料の納付について
(保険料の納付方法、納付相談、納入通知書に関することなど)
総務部税務課徴税係・収納係
Tel:0875-23-3922