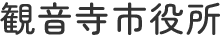本文
【ふるさと学芸館】「あれやこれや」(令和7年4月)について
毎月、ふるさと学芸館「今月の一品」として、収蔵品の紹介を行なってきましたが、今月からは、「あれやこれや」とタイトルを変え、収蔵品だけではなく、ふるさと学芸館に係る様々なトピックを紹介していきます。
ふるさと学芸館「あれやこれや」 今月は・・・
「五月人形(神功皇后(じんぐうこうごう)・武内宿禰(たけのうちのすくね)」
です!

4月半ばから5月末まで、本館の多目的ルームを五月人形が彩ります。その中でもとりわけ歴史を感じるのが、軍配を振るう「神功皇后(じんぐうこうごう)」と赤子を抱く「武内宿禰(たけのうちのすくね)」です。
神功皇后は夫の仲哀(ちゅうあい)天皇の崩御後、そのあとを受け、子どもをお腹に宿したまま朝鮮半島へと出兵しました。朝鮮へ攻め込む勢いはすごく、「船が山に登らんばかりだった」という言い伝えが残るほどです。
また、皇子(後の応神(おうじん)天皇)を出産した翌年には、反乱を数万の軍勢を率いて鎮圧したそうです。その際、赤子である皇子を抱きながら神功皇后を補佐したといわれているのが武内宿禰です。
武内宿禰は、神功皇后だけでなく、仲哀天皇、応神天皇と、その前二代、その後一代の天皇に仕えたとされています。『因幡国風土記(いなばのくにふどき)』には360歳まで生きたという伝説が記されています。
そして、1889年から1958年まで69年間発行された「改造壱円札」の肖像にも用いられ、最も長く紙幣に描かれた人物としても知られています。本館には、この「改造壱円札」も展示しています。ぜひ五月人形とともにご覧ください。