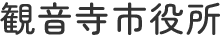本文
【ふるさと学芸館】「あれやこれや」(令和7年9月)について
ふるさと学芸館「あれやこれや」 今月は・・・
「元号」
です!
令和7年の今年は「昭和100年」と表現されることがあります。見聞きした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「令和」や「昭和」などの元号は中国を起源として漢字文化圏に広がったものですが、現在公的に制定、使用されているのは日本のみとなっています。 日本の元号は、「無事故で世直し大化の改新」で覚えられた645年の「大化」で始まりました。その後、使用されなかった期間もありますが、701年の「大宝」からは現在の「令和」まで連綿(れんめん)と続き、合わせて248もの元号が制定されています。その中で、最も長い期間使われたのが「昭和」で62年、最も短かったのが鎌倉時代初期の「暦仁(りゃくにん)」の2カ月です。
使用された漢字は意外と少なく73文字で、最も多く使われたのが「永」で29回、次いで「元」、「天」の27回です。ちなみに「和」は20回、「令」は今回初めて使われています。そして、大部分の元号は漢字2文字ですが、奈良時代には「天平感宝(てんぴょうかんぽう)」、「神護景雲(じんごけいうん)」など、4文字のものが5つ制定されています。
また、江戸時代中期に制定され、その9年目に大火や天災が相次ぎ、「迷惑(めいわく)年(ねん)」という別名が巷(ちまた)に広まった「明和」という元号もあります。
そうした「248の元号」が、本館2階にズラリと並んでいます。ぜひともご来館のうえ、日本の時代の流れを感じ取っていただけたらと思います。