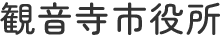本文
【ふるさと学芸館】「あれやこれや」(令和7年11月)について
ふるさと学芸館「あれやこれや」 今月は・・・
「借耕牛(かりこうし)」
です!
香川・徳島県境の道路に、米俵を乗せた牛を引いている様子が描かれた橋があります。これは「借耕牛(かりこうし)」というもので、農繁期に徳島から来ていた牛に労働の対価としての米を背負わせ、徳島へ連れ帰っている様子を表しています。
徳島県の北西部は、山間部が多く、牧草が豊富で牛が飼いやすい反面、耕作には不向きでした。それに対して、香川県の平野部は水田が多いため、飼料となる草資源が乏しく、耕作に必要な牛を飼うことができなかったのです。こうした背景から「借耕牛」が生まれました。
借耕牛は、江戸時代の中期の文化年間(1804~1818年)ごろに始まったといわれ、明治30年ごろから盛んになりました。多い時期には8千頭を超える牛が、五名(ごみょう)(東かがわ市)、清水(しみず)(三木町)、岩部(いわぶ)(高松市)、見合(みあい)、塩入(しおいり)(まんのう町)、猪ノ鼻(いのはな)、野呂内(のろち)(三豊市)、曼陀(まんだ)(観音寺市)などから県境の山々を越えたとされています。
しかし、農業の機械化が進むにつれて数も減少し、昭和30年代には、その姿も見られなくなりました。
本館には、牛が道草を食べないようにする「口籠(くつご)」や米を背負うときに用いた「鞍(くら)」、山道を歩くために履かせた「草履(ぞうり)」など、借耕牛に由縁のあるものを展示しています。ぜひ、ご来館の上、ご覧いただけたらと思います