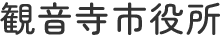本文
令和7年度 高齢者帯状疱疹予防接種(定期)
高齢者帯状疱疹ワクチンの定期予防接種が始まりました。
対象の方には5月中に予診票などの案内を送付しています。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は子どもの頃に感染した水痘・帯状疱疹ウイルスが神経節に潜み、過労やストレス、加齢など免疫が低下した際に再び活性化して発症します。
50歳以上になると発症する人が増加し、80歳までに約3人に1人が発症すると推定されています。
発症すると体の左右どちらかの神経節に沿って、痛みを伴う発疹と水ぶくれが多数集まって帯状に生じます。
皮膚症状が治った後も、50歳以上の約2割に帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼ばれる痛みが長期間続くことがあります。
帯状疱疹の発症予防のためには、予防接種を受けるほか、規則正しい生活習慣の維持や適度に体を動かすなど、帯状疱疹になりにくい体づくりが大切になります。
接種期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
対象者
接種日に観音寺市に住民登録がある方で、
(1)年度内に65歳を迎える方
(2)60~64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
(身体障害者手帳1級を有する方)
経過措置期間
経過措置の期間中は以下の方も対象となります。
・令和7年から令和11年(5年間)の各年度において、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方
・令和7年度において、100歳以上の方
令和7年度の対象者は以下のとおりです。
| 年齢 | 生年月日 |
|---|---|
| 65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 |
| 70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 |
| 75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 |
| 80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 |
| 85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
| 90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 |
| 95歳 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 |
| 100歳 | 大正14年4月2日~大正15年4月1日 |
| 101歳以上 | 大正14年4月1日以前に生まれた方 |
ワクチンの種類、自己負担額など
|
種類 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン 「ビケン」(生ワクチン) |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 「シングリックス」(組換えワクチン・不活化ワクチン) |
|---|---|---|
| 接種回数 |
1回 |
2回 (1回目の接種から2か月後に2回目の接種を行う) |
| 自己負担額 |
【課税世帯の方】 2,700円 【非課税世帯の方】 無料 【生活保護世帯の方】 無料 |
【課税世帯の方】 13,400円(6,700円×2回) 【非課税世帯の方】 8,000円(4,000円×2回) 【生活保護世帯の方】 無料 |
| 接種方法 | 皮下注射 | 筋肉注射 |
| 発症予防効果 |
1年後で6割程度 5年後で4割程
|
1年後で9割以上 5年後で9割程度 10年後で7割程度 |
| 頻度10%以上の副反応 |
発赤*、そう痒感* 、熱感* 腫脹* 、疼痛* 、硬結* ( *ワクチンを接種した部位の症状) |
疼痛*、発赤*、筋肉痛、疲労、頭痛、腫脹*、悪寒、発熱、胃腸症状 (*ワクチンを接種した部位の症状) |
|
重大な副反応 (いずれも頻度不明) |
アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎 |
ショック、アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群 |
出典:厚生労働省ワクチン分科会資料、取扱説明書(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
乾燥組換え帯状疱疹ワクチンシングリックス筋注用)
厚生労働省帯状疱疹の予防接種についての説明書より
※ 合併症の一つである帯状疱疹後神経痛(PHN)に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、不活化ワクチンは9割以上と報告されています。
※乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)は、明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する方及び免疫抑制をきたす治療を受けている方、妊娠していることが明らかな方は接種を受けることができません。
自己負担金免除
市民税非課税世帯または生活保護世帯に属する方は自己負担金が一部または全額免除となります。
接種前に証明書をご準備ください。
(下記ア~オのうち1点)
※ 接種後の払い戻しはできません。
| 免除対象者 | 証明書名 | 申請方法 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
|
非課税 世帯の方 |
ア. 介護保険料額決定通知書 |
1.令和7年度に発行された最新のものを準備 (令和7年4.5.6月に接種される方は令和6年度のもの) 2.接種を受ける本人のものであるか確認 3.所得段階が1~3段階であるか確認 4.所得段階が1~3段階であった方は、A4サイズの紙に所得段階が書いてあるページを事前にコピーをして、予診票と共に医療機関へ提出してください。 |
・未申告のものは使用できません。税務課で申告をしてください。 ※紛失された場合は再発行できませんので、エの申請をお願いします。 |
| イ. 介護保険料納入通知書 | |||
| ウ.介護保険負担限度額認定証 |
1.接種を受ける本人のもので、有効期限内であることを確認 2.A4サイズの紙に事前にコピーをして、予診票と共に医療機関へ提出してください。 |
||
| エ. 高齢者定期予防接種自己負担金免除対象世帯証明書 |
健康増進課(本庁舎1階4番窓口)または各支所まで申請に来てください。 【持ってくる物】 (1)接種を受ける本人の予診票 (2)接種を受ける本人の身分証明書 (運転免許証、健康保険の資格確認書、マイナンバーカード等) |
・接種前に申請に来てください。 ・代理人の方が申請に来られる場合は (1)接種を受ける本人の予診票 (2)接種を受ける本人の身分証明書(運転免許証、健康保険の資格確認書、マイナンバーカード等) (3)代理人の身分証明書(顔写真入りのもの1点もしくは顔写真なしのもの2点) を持って来てください。 |
|
|
生活保護 世帯の方 |
オ. 生活保護受給証明書 |
本庁舎1階7番窓口まで申請に来てください。 【持ってくる物】 (1)接種を受ける本人の予診票 |
・接種前に申請に来てください。 ・令和7年度発行のもので、使用目的が帯状疱疹予防接種と記載されたもの |
※1回の接種つき1枚証明書が必要です。
(不活化ワクチンを2回接種する予定の方は、2枚証明書が必要です。)
※令和7年1月2日以降に観音寺市へ転入された方は健康増進課へお問い合わせください。
他のワクチンとの同時接種・接種間隔
いずれの帯状疱疹ワクチンについても、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。
ただし、生ワクチン(阪大微研)については、他の生ワクチンと27 日以上の間隔を置いて接種してください。
接種までの流れ
1.送付された案内をよく読み、接種するワクチンの種類を決定する。
2.接種を希望する医療機関へ接種の予約をする。
3.予診票に必要事項を記入する。
4.予約した日時に予診票、本人確認ができるもの、自己負担額を持参し、実施医療機関で接種を受ける。
5.接種費用を支払う。
実施医療機関
高齢者帯状疱疹定期接種 実施医療機関一覧表 (観音寺市・三豊市) [PDFファイル/145KB]
(香川県内広域協力医療機関でも接種可能)
※県内協力医療機関で予防接種を受けることが難しい場合は事前に市へお問い合わせください。
予防接種健康被害救済制度
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。
万が一、定期予防接種による健康被害が生じた場合に、厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
申請方法などご不明な点については、健康増進課までお問い合わせください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
よくあるお問い合わせ
Q1.65歳の時に接種を受けなかったとしても、70歳の時に接種できますか?
70歳の時には定期接種の対象とはなりません。
定期接種として助成を受けられるのは、生涯一度だけです。
Q2.帯状疱疹にかかったことがありますが、接種できますか?
帯状疱疹にかかったことがある方も定期接種の対象とします。
接種する時期などはかかりつけ医や接種医にご相談ください。
Q3.帯状疱疹ワクチンを接種したことがありますが、接種できますか?
過去に帯状疱疹ワクチンを接種したことがある方は、基本的には定期接種の対象外となります。
ただし、医師が接種が必要と判断した場合は接種対象者となる場合があります。
Q4.1回目に生ワクチンを接種し、2回目に不活化ワクチンを接種できますか?
どちらか一方のワクチンしか接種できません。
Q5.不活化ワクチンは2回接種すると聞きました。1回目はいつ接種したらいいですか?
令和8年3月31日までに2回目を接種する必要がありますので、1回目の接種は12月末までには終わらせましょう。
なお、令和8年4月1日以降に接種した場合は、任意接種となり接種費用が異なりますのでご注意ください。
Q6. 定期接種の対象ではないのですが、帯状疱疹ワクチンを接種したいです。
観音寺市に住民票がある、満50歳以上の方には帯状疱疹予防接種の費用を一部助成しています。
詳しくは帯状疱疹予防接種費用の一部助成をご覧ください。
Q7. 今年度の対象者です。誕生日を迎えてから、接種するのでしょうか?
対象者は誕生日を迎える前でも期間中(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)は接種できます。
医療機関の方へ
・請求書をダウンロードして、請求書と予診票を添えてお送りください。
(自己負担金免除の場合は、免除のための証明書を添付してください。)
令和7年度B類請求書一式 [Excelファイル/416KB]
・翌月10日締め、月末支払いです。
郵送の場合は、10日必着となるように送付してください。
10日を過ぎますと、翌月払いになりますので、あらかじめご了承ください。
・3月分の請求は、請求書の右上の日付を「令和8年3月31日」とご記入ください。