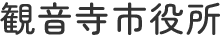本文
伊吹島(いぶきじま)
地形
観音寺港沖約10km、周囲5.4Km、面積1.01平方kmの島で、香川県の西端にあります。
伊吹島は、安山岩、花崗岩などからなる台状の島です。島の周囲は急傾斜の崖が海岸沿いにそびえたち、住宅は島の南から北にかけての鞍部に集中しています。

名前の由来
神恵院の住職であった弘法大師が、島の近くの海に漂っていた光を放つ不思議な木、「異木(いぼく)」を引き上げ、多くの仏像を刻まれたことから「異木島(いぼくじま)」と名付けられたといいます。
また、一説では島の西浦の沖合いに海底から泡が吹き出しているところがあり、大地が息を吹いている「息吹(いきぶき)」が訛って、「伊吹島」と呼ぶようになったともいわれています。
島のことば
伊吹島の言語は独特の特徴を持ち、古語に属する方言や特殊な敬語が使われ、平安時代のアクセントが残っています。
言語学上貴重な島であることから、国語学者の金田一春彦先生も二度、伊吹島を訪れました。
その際に詠んだ歌が歌碑に刻まれ、建立されています。
島の名所
伊吹島全体が新さぬき百景に登録されており、随所に見所があります。
イリコ(煮干し・イワシ)加工場
海岸沿いにはイリコの加工場が立ち並び、伊吹島ならではの風景が広がります。
真浦港から東側のエリアに特に集中して加工場があります。
石門
海水の浸食によって作られた石門は、伊吹島の中でも代表的な場所です。
干潮時にはぽっかりと開いた穴を見ることができます。
※令和6年7月2日、石門を見ることができる地点までのルートで落石がありましたので、通行には充分ご注意ください。
合戸の穴
別名、「強盗の穴」とも呼ばれています。
その昔、海賊が隠れ住んでいたという伝説が残っています。
出部屋(旧伊吹産院跡)
昭和45年ごろまで、出産を終えた母子が1か月間共同で暮らす産院がありました。
建物は残っていませんが、当時の門柱が残っています。
伊吹島民俗資料館
旧伊吹幼稚園を利用した島民手作りの資料館です。農具や漁具、写真などが多数展示してあり、伊吹島の歴史や文化を知ることができます。
秋には庭にアサギマダラという渡り蝶が飛来します。
伊吹八幡神社
島民の氏神様です。初夏には絵馬堂でお神楽が、秋には3台の太鼓台が奉納されます。
泉蔵院
正式な名称は、真言宗大覚寺派七宝山泉蔵院。
旧暦の3月21日に行われる島四国の出発寺院です。

荒神社・西の堂
荒神社では初夏に、かがり火のもと、夜神楽が奉納されます。
西の堂には、伊吹島の女性たちが行う娘遍路の写真などが飾られています。西の堂は、島四国の最後にお参りする寺院です。

波切不動尊
島の北端の断崖に祀られたお不動さんです。島の人たちに「お不動さん」と呼ばれ、親しまれています。
桜のアーチと瀬戸内海が同時に楽しめる桜の名所で、桜まつりも開催されます。
大師堂
弘法大師をお祀りしている大師堂です。島四国のときには大勢の参拝客でにぎわいます。

ハートのベンチ
恋人と一緒に来たらぜひ一緒に座ってほしい、ハートの形をしたベンチです。
夕陽が沈むのを2人で一緒に見ると、幸せになると言われています。
大きなイス
島民が手作りした高さ約3.5mもある大きな木のイスです。知る人ぞ知る、夕陽の穴場スポットです。
産業
良質なイリコの生産が盛んで「イリコの島」として有名です。
漁期の6月から9月、島は活気にあふれます。

主な行事
| 開催月 | 行事名 |
|---|---|
| 2月 | 百手祭 |
| 4月 | 波切不動尊の桜まつり |
| 4~5月(旧暦3月21日) | 島四国 |
| 6月 | お神楽 |
| 7月 | 港まつり(明神祭) |
| 10月 | 秋祭り |
瀬戸内国際芸術祭
2013年、2016年、2019年、2022年の会場となりました。
「トイレの家」「イリコ庵」「伊吹の樹」の3作品は現在もご覧いただけます。
「トイレの家」石井大五 作
「イリコ庵」 みかんぐみ+明治大学学生 作
「伊吹の樹」栗林隆 作
アクセス
観音寺港まで
車
高松自動車道大野原ICから車で15分(約6km)
さぬき豊中ICから車で20分(約8km)
鉄道
JR観音寺駅から観音寺港までタクシーで約5分、徒歩約25分
のりあいバス
のりあいバスは1日7便。
JR観音寺駅からのりあいバス内循環線に乗り、運転手に「観音寺港」と告げてください。
のりあいバスにはバス停がなく、路線上ならどこでも乗り降り自由です。
(ただし、国道11号線は指定場所以外、乗り降り禁止)
観音寺港から真浦港(伊吹島)まで
定期船で25分
大人(中学生以上):600円、小人(小学生のみ):300円 小学生未満:無料
お問い合わせ
伊吹支所
Tel:0875-29-2111
商工観光課
Tel:0875-23-3933