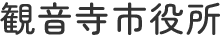本文
国民健康保険税について
国民健康保険は、加入者の国保税と国や自治体が負担する公費などを財源として、医療給付を行う医療保険制度です。
国保税は、加入者の皆さんが安心して治療・診療を受けるための大切な財源です。期限内の納付にご協力ください。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です
国民健康保険税(以下、国保税)の納税義務者は世帯主です。例えば、世帯主が会社の社会保険に加入されている世帯で、世帯主以外の方が国民健康保険に加入された場合、国保税の納税通知書は世帯主のお名前でお送りします。また、世帯主が後期高齢者医療制度に加入されている場合も同様です。
国保税の簡易算出方法
・加入者(被保険者)の中に40歳から64歳の方がいる世帯・・・・・(1)+(2)+(3)の合計額
・加入者(被保険者)の中に40歳から64歳の方がいない世帯・・・(1)+(2)の合計額
| 所得割 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|
| (前年中の総所得金額等-43万円)×8.7% | 被保険者1人あたり 27,000円 |
一世帯あたり 28,000円 |
| 所得割 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|
| (前年中の総所得金額等-43万円)×2.4% | 被保険者1人あたり 7,200円 |
一世帯あたり 4,500円 |
| 所得割 | 均等割 | 平等割 |
|---|---|---|
| (前年中の総所得金額等-43万円)×1.0% | 被保険者1人あたり 6,200円 |
一世帯あたり 4,000円 |
備考
- 今年度中に資格異動(転入・転出・死亡等)があった場合には、資格異動日より月割りで賦課します。
- 今年度3月までに年齢が65歳に達する方の介護納付金分は、65歳に達する前月までの月割りで賦課します。今年度7月以降に年齢が40歳に達する方の介護納付金分は、40歳に達する月から新たに月割りで介護納付金分を賦課し、後日通知します。また、75歳になられて後期高齢者医療制度へ移行する方の国保税は、75歳に達する前月までの月割りで賦課します。75歳に達する月から月割りで賦課される後期高齢者医療保険料については、75歳に達した後に通知します。
所得状況の申告
国保税を正しく算定するために、前年中の所得を把握する必要があります。収入がない、非課税年金(遺族年金や障害年金)収入のみ、確定申告が必要ない、という場合でも申告が必要です。市税務課で申告を行うか、簡易申告書様式を印刷して必要事項を記入の上、提出してください。
簡易申告書の様式
提出先
持参の場合
税務課(市役所1階3番窓口)、各支所
郵送の場合
〒768-8790
香川県観音寺市坂本町一丁目1番1号
観音寺市総務部税務課市民税係 行
納付方法
普通徴収(納付書・口座振替)
納付書で納付する方法と、口座振替の方法があります。
納期限
| 期別 | 1期 |
2期 |
3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期限 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 |
12月25日 |
1月末 |
2月末 |
※納期限が土曜日、日曜日または祝日のときは、その翌営業日が納期限です。
特別徴収(年金天引き)
賦課期日(4月1日)に以下の条件をすべて満たす方は、10月に受給する公的年金から特別徴収(年金天引き)が開始されます。
- 世帯内の国保被保険者「全員」が65歳以上75歳未満である世帯の世帯主の方
(ただし、年度途中で世帯主・被保世帯員が65歳または75歳になる世帯では、特別徴収(年金天引き)は行いません。) - 特別徴収対象年金受給額が年額18万円以上の世帯主の方
- 介護保険料が特別徴収されている世帯主の方
- 介護保険料と国保税の合算額が特別徴収対象年金受給額の2分の1以下の世帯主の方
特別徴収(年金天引き)を継続している方
特別徴収(年金天引き)の条件を満たす方は、引き続き、公的年金から国保税の年税額を6回(仮徴収3回・本徴収3回)に分けて天引きします。
仮徴収 : 4月、6月、8月
- 前年度の2月徴収分と同額を天引きします。
本徴収 : 10月、12月、2月
- 7月に確定した国保税の年税額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて天引きします。
国保税の減免
所得が少ない方に対する軽減
世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した総所得金額等の合計額(前年所得)が、一定水準以下の場合(会社の社会保険や後期高齢者医療制度に加入されている世帯主の所得も含む)、均等割額と平等割額を各割合で軽減します。
- 7割軽減基準額 43万円+10万×〔※給与所得者等の数-1〕
- 5割軽減基準額 43万円+30.5万円×〔被保険者数〕+10万×〔※給与所得者等の数-1〕
- 2割軽減基準額 43万円+56万円×〔被保険者数〕+10万×〔※給与所得者等の数-1〕
※給与所得者等・・・一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
太字部分については、給与所得者等の数が2人以上の場合にのみ計算されます。
非自発的失業者に対する軽減
会社の倒産や解雇、雇い止めなどで職を失った方(非自発的失業者)が安心して医療を受けられるよう、申請することにより国保税が軽減されます。対象者は、前年の給与所得を100分の30として、国保税の算定および高額医療費等の所得区分の判定を行います。
なお、軽減の対象や軽減期間等の制度の詳細は、国民健康保険税の軽減制度についてをご覧ください。
産前産後期間の免除
出産する予定がある方または出産した方は、産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます。制度の詳細は、産前産後期間の国民健康保険税の免除についてをご覧ください。
介護保険適用除外施設
介護保険適用除外施設に入所・入院されている介護保険第2号被保険者の方は国保税の介護納付金分を納付する必要がありません。介護保険適用除外施設に入所または退所された場合、14日以内に高齢介護課介護保険係(Tel.23-3968)まで届け出てください。